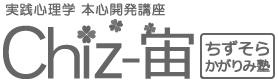【夢工房500字エッセイ】さくら
夫も子も持つ身でありながら恋をしたことがある。
今から十年ほど前のこと。
そのひとは私より五つほど年上で、矢沢永吉に似ていて、バツイチで、商社マンで詩人だった。
おそるおそる始まった私たちの交際は、小指の先も触れ合わぬまま、正しく季節を重ねた。
彼はよく手紙を書くひとで、来週もまた会えるのに、封を切れば歌うような便りがポストに届くのだった。
まだ春浅い日。彼のお父様が亡くなった。
それからほどなく彼から届いたのは、大きな大きな宅配便。
開けるとそれは額に入った、淡いピンクの桜の水彩画だった。眺めるほどに胸の奥までその色に染まってしまいそうだ。
それは彼のお父様が描かれたものとのこと。見慣れた筆跡でメッセージがあり、「大切なものだから、あなたに持っていてほしい」と。
彼が不意に投げてよこしたボールはずしりと重くて、うれしいのに悲しい。
私はゆらゆら途方に暮れた。
それからしばらくぎこちない交際は続いたが、ある日彼の手紙を読まずにそのまま送り返したのが、私たちの最後になった。
月日の中でこの恋を人に語れるようになった頃、彼の訃報を受け取った。
その報せを手に突っ立って泣いた。
桜にまだ早いこの季節には、あの絵の桜色が胸に拡がってせつない。
(現代川柳ゆうゆう夢工房2010年3月3日掲載分)
中川千都子の既発表エッセイを不定期にお届けします。
2016.3.30