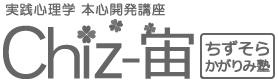【ときめき地図】ひゃくねん
花火を見に行こう、とその人から誘いを受けたとき、私の中で花火が上がった。
黙っていると、長身を屈め「行ける?」と顔を覗き込まれてしどろもどろになった。
「え?あ?たぶん、なんとかなります」。
さして予定もなかったのに忙しいふりをして、にこりともせずに答えた。
そしてその日から花火までを指折り待った。
ひときわ蒸す夕暮れだった。
そのうえ、どこから人が湧いてくるのか、花火大会の行われる河川敷まで、夥しい人の波は途切れることがない。
粘るような暑さと人いきれ。
くらくらしてしまう。
くらくらするのは、あるいは隣の人とこんなにも寄り添っているせいか。
人込みに押されるまま、寄り沿い合い、傍目には私たちはきっと恋人たちのようだろう。
相手の体温を感じながら、この人が私にとってどんどん特別になってゆくのを止められない。
目指す河川敷にたどり着き、土手の柔らかい草の上に私たちは腰をおろした。
どこかの窓やベランダから遠い空の花火を見たことはあったが、わざわざ見に来たのは初めてである。
しかしその光景は、思っていたほどロマンチックなものでもなく、見渡せば何組かの恋人たちと、あとは賑々しい若者たちのグループや、走り回る子どもたちを声高に追いかける家族連れが何組か。
七月の明るい夕暮れにも、ようやく淡い闇が広がり始めた。
どさりと鞄を倒すと、彼はそれを枕に草の上に寝転がった。
私も促されるままに寝転がってみると、空はさらに大きく私の上に広がった。
先ほどまで他愛ない話をしていた私たちだったが、どちらからともなく黙って、吸い込まれるように空だけを見ていた。
ドン!と大きな音とともに一発目の花火が打ち上がった。
あぁ、と嘆息のように声が洩れた。
開いた花火はみるみる空に散り、また新たな花火が打ち上がる。
あぁ。
次々打ち上げられては消えてゆく花火を眺めていると、うろ覚えながらふと俵万智の歌の下の句が浮かんできた。
「・・・ひゃくねんたったらだあれもいない」
百年経ったら誰もいない。
例外なく。
ここにいるあの若者たちも、さっき子どもを叱っていたお母さんもその子どもでさえも、百年経ったらいなくなる。
そう、いま隣に居る人も。
もちろん私も。
花火はいよいよ華やかに空を彩る。
「ひゃくねんたったらだあれもいない」
私の中でそのフレーズはこだまし続ける。
*参考「地ビールの泡(バブル)優しき秋の夜 ひゃくねんたったらだぁれもいない(俵万智)」
*「現代川柳」2015年7月号掲載。「ときめき地図」は、川柳文芸誌「現代川柳」に連載中の中川千都子のエッセーのコーナーです。
2021.7.24